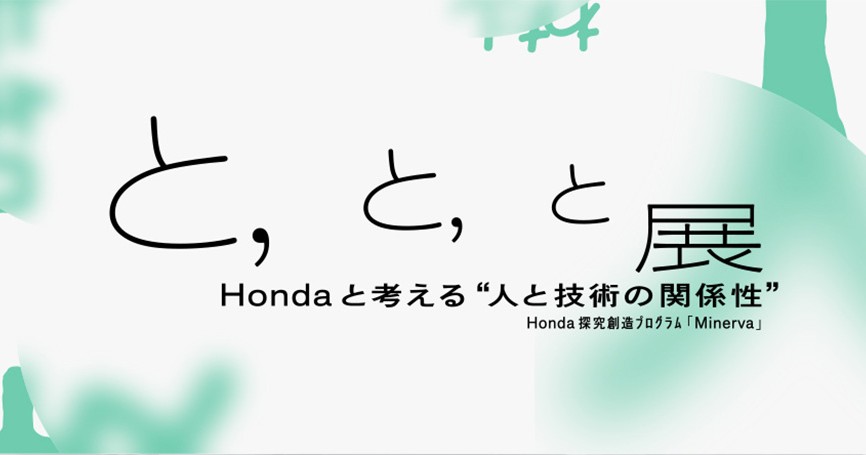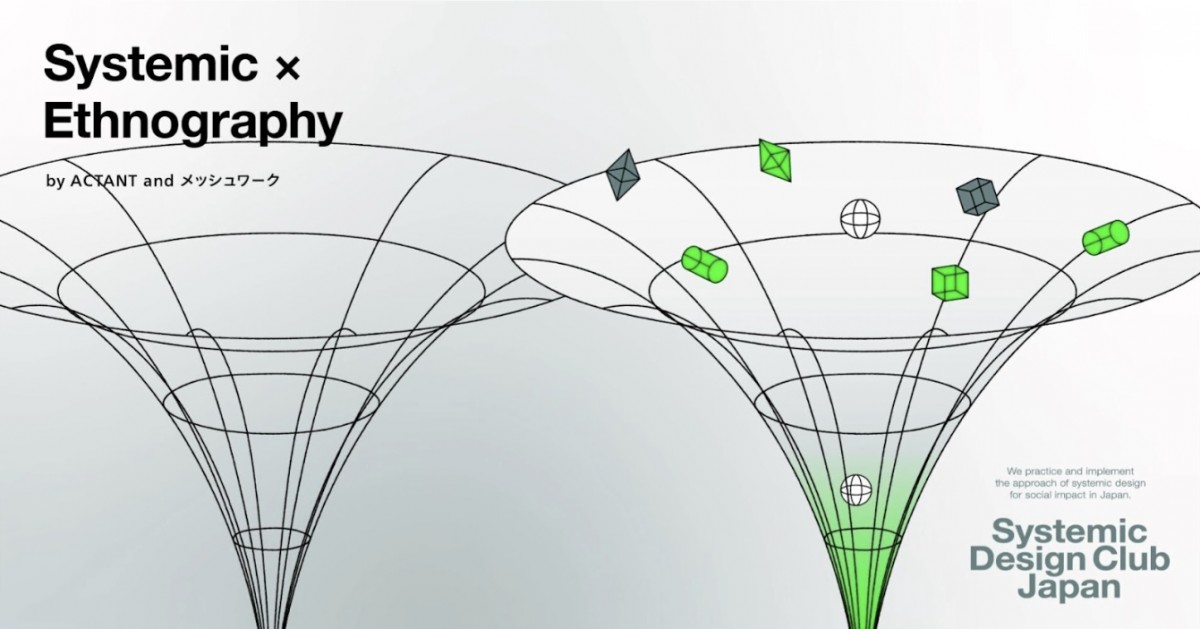人類学的感受性へ【メッシュワーク年頭挨拶】
皆様、新年あけましておめでとうございます。
日頃よりメッシュワークを応援してくださり、ありがとうございます。
新たな年を迎えるにあたり、これまでの出会いや経験を大切にしながらも、新しいことへと柔軟に挑戦しつづける私たちでありたいと思っています。
以下は比嘉による年頭の所感です、よろしければご笑覧ください。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2024年1月5日 合同会社メッシュワーク一同
人類学的感受性へ
Toward an Anthropological Sensibility
あたらしい年が来た。
けれど、災禍は止まない。
戦争のような人災も、地震のような天災も、人びとの平穏な日常に容赦なく襲いかかる。
国内外の遠く離れた地からもたらされる悲痛な知らせに、私たちは心を痛める。
その地域に暮らす友人の安否を気遣ったり、かつて訪れたときの記憶と照らして悲しい気持ちになったり、語りや映像や活字をとおして生の声に触れ、壮絶さに言葉を失ったりする。
人間の生存を左右するような局面になると、私たちの感受性は、普段よりいくらか研ぎすまされる。そこで何が起きているのか、人びとが何に直面し、何を感じ、何を求めているのか、できるだけ察知しようとする。
それでも、私たちはいつか忘却する。
悲惨な状況、それに伴うひりひりとした感情、一連の記憶は、時が経つにつれて徐々に薄れ、人びとはまたそれぞれの日常へと戻っていく。
当事者から遠い立場であればなおさらだ。忘却それ自体は、不可避なことだ。世間の話題は移ろい、表面的には平穏さを取り戻し、一時は鋭く尖っていたはずの「世界を感受するアンテナ」も、ぼんやりと鈍くなっていく。
「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」
と、詩人である茨木のり子は言った。
記憶は時間とともに消えていくし、感受性だって意識して守らなければいとも簡単に失われてしまう。それは厳しい現実だけれど、逆にいうなら、きちんと守りつづけさえすればいいのだ。世界を感受するために、つい忘れがちな自分へのリマインドを、絶えず心がけていればいいのだ。
人類学者は、フィールドへと飛び込み、そこに生きる人びとと関わることを通じて、世界の複雑さや不条理さ、人間の生の多様さを、そのつど彼らからリマインドしてもらっている。「感受性くらい」「自分で守れ」と茨木のり子は言うけれど、人類学者はおそらくその感受性を、他者の助けをおおいに借りることによって、保っている。
ここでいう感受性sensibilityは、sense(感じる/意識する/察知する)+ability(能力)のことだ。人類学的感受性は、生まれもった能力や、特定の人だけが持つ(日本語的なニュアンスの)「センス」なのではない。それは私たちの日々の行為のなかに宿り、他者と過ごす時間のなかで少しずつ養われていくものだ。
ほうっておけば狭まり、固着し、ついには失いかねない自分の感受性を、人びとと互いに助けあいながら、なんとか保ち、のびやかに育てていく。特別な事件や明確な社会問題だけではなく、日常に宿る些末な行為のきらめきや、個々人の感情の機微をも、感じ、意識し、察知していけるように。
それは必ずしも簡単なことではないかもしれないが、けっして不可能なことではない。孤独に頑張らなくてもいい、他者と常に真摯に向きあいながら、人類学的感受性を一緒に育てていこう。
やがて世界は、私たちの眼前に、一層くっきりと、奥行きをもって、現れてくるだろう。

すでに登録済みの方は こちら